「石垣島に観光客は来ないで」—この言葉を聞いて、あなたはどのように感じるでしょうか。
美しい海と豊かな自然で知られる石垣島から、なぜこのような声が上がったのか疑問に思う方も多いでしょう。
実は、この言葉の背景には石垣島が直面した深刻な事情があります。
新型コロナウイルスの感染拡大という未曾有の危機の中で、島民の命と健康を守るために下された苦渋の決断。
しかし、時は流れ、現在の石垣島はどのような状況なのでしょうか。本記事では、「観光客は来ないで」と言われた当時の状況から、現在の観光事情、そして持続可能な石垣島観光の未来について、最新の情報をもとに詳しく解説します。
石垣島への旅行を検討している方、または石垣島と観光の関係について気になる方の参考になれば幸いです。
石垣島が「観光客来ないで」と訴えた本当の理由

2020年4月6日、石垣市は新型コロナウイルスの島内感染拡大を防ぐため、観光客をはじめとする来島自粛を強く呼びかけました。
この決断の背後には、以下のような石垣島特有の深刻な事情がありました。
医療体制の脆弱さ
石垣島の医療体制は、本土と比べて非常に限られていました。
当時、島内で新型コロナ感染者を受け入れられる病床は、県立八重山病院にわずか3床のみ。人口約5万人の島にとって、この数字は心もとないものでした。
もしも感染が一気に広がれば医療崩壊は避けられなかった。
こうした石垣島の医療体制の脆弱さが大きく影響していました。
「沖縄の離島は安全」――危険な誤解
インターネットやSNSでは、「沖縄の離島はコロナから安全」といった誤った情報が拡散され、都市部から「コロナ避難」として石垣島に向かう人が増加する懸念も高まっていました。
しかし現実には、医療体制が脆弱な離島こそ、感染が拡大すれば甚大な被害を受けるリスクが高かったのです。
この誤解は、島民の不安と警戒心をさらに強める結果となりました。
島民の生の声と当時の心境
【日常生活での緊張と不安】
当時の石垣島では、住民の多くが日々、感染への恐怖と隣り合わせの生活を強いられていました。
スーパーやドラッグストアなどで観光客らしき人を見かけるたび、「感染を持ち込んでいるのでは…」という不安がよぎったといいます。
これは決して観光客への差別ではありません。離島という閉鎖的な環境で、外部からのウイルス流入を防ぐことは、島全体の命運を左右する重大な問題だったのです。
【「観光客お断り」の張り紙が広がった背景】
この時期、多くの飲食店や施設で「観光客お断り」という張り紙が掲げられました。これは営業判断というよりも、島民の命を守るための“防衛反応”だったのです。
訪れた観光客の中には、島に到着して初めてこの現実に直面し、戸惑う人も少なくありませんでした。
石垣島観光ブームの光と影|島民が直面した現実とは?
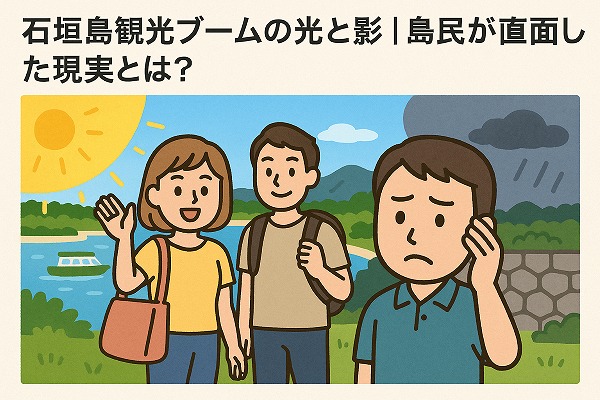
石垣島はその美しい自然と独特の文化で、長らく「日本の楽園」として多くの観光客を惹きつけてきました。
特にコロナ前の数年間は、観光客数が急増し、島全体が活気に満ちあふれていました。
しかし、その裏側で静かに進行していたのが、“観光地化の代償”とも言える問題の数々です。
観光ブームに沸いたコロナ前の石垣島
コロナ以前の石垣島は、まさに観光ブームの真っ只中にありました。
LCC(格安航空会社)の就航やインスタグラムなどSNSの拡散力が後押しとなり、石垣島を訪れる観光客は年々増加。
2019年には、年間およそ140万人もの観光客が訪れるようになり、石垣島は国内外から熱い注目を集めていました。
中でも、川平湾のエメラルドグリーンの海、ブランド牛・石垣牛を楽しめるグルメ、そしてダイビングやシュノーケリングなどのマリンアクティビティが人気を博し、多くのリピーターを生んでいました。
石垣島の経済を支える観光業
観光業は石垣島の経済を支える大黒柱となっていました。
ホテルや民宿などの宿泊業はもちろん、飲食店、小売店、交通機関、マリンレジャー会社など、観光に関わる業種は多岐にわたります。
島民の多くが観光業に従事しており、その経済効果は税収にも大きく貢献。道路や公共施設の整備など、インフラの充実にもつながっていました。
まさに観光は「島を豊かにする原動力」として、大きな期待を背負っていたのです。
観光ブームの裏にあった“ひずみ”
しかし、急激な観光客の増加は、島の生活環境に大きなゆがみをもたらし始めていました。
石垣島の人口は約5万人。それに対して年間140万人の観光客が訪れるということは、単純計算で島民1人あたり28人の観光客を受け入れていることになります。
この比率は国際的に見ても非常に高く、明らかに“オーバーツーリズム”の兆候を示していました。
増えすぎた観光客がもたらしたインフラへの負担
1. 水道供給のひっ迫
石垣島の水は限られた資源であり、一部は地下水や海底送水に頼っています。
観光シーズンになると水の使用量が急増し、地元住民の生活用水への影響が懸念される場面もありました。
2. 電力需要の急増
リゾートホテルや飲食店、商業施設の増加により電力消費量が大幅に上昇。電力供給の安定性にも影響が出始めていました。
3. 交通渋滞の慢性化
観光客によるレンタカーの利用が急増し、狭い島の道路は常に渋滞気味に。特に夏休みや連休中は、市街地や空港周辺で交通が麻痺することもありました。
4. ゴミ処理の限界
観光客が出すゴミの量が膨大になり、島のゴミ処理施設が対応しきれない事態に。結果として、不法投棄や環境汚染のリスクも高まっていたのです。
島民の生活に押し寄せた変化
観光客の急増は、島民の暮らしにも少なからぬ影響を及ぼしていました。
たとえば、以前は静かだった住宅街にまで観光客が入り込み、夜間の騒音やマナーの問題が発生。また、観光スポット周辺の駐車場不足により、生活道路がふさがれてしまうケースも。
さらに、観光業の活性化により地価が上昇し、地元の若者や新婚世帯が住宅を確保しにくくなるといった「暮らしの格差」も生まれていました。
【現在の状況】石垣島観光の復活と新たな課題

観光客と移住者の回復傾向
2023年以降、観光客数は回復傾向に
新型コロナウイルスの影響が落ち着き始めた2023年以降、石垣島への観光客数は徐々に回復しています。
政府の旅行支援策や航空便の正常化も後押しし、2024年にはコロナ前の約7割まで回復したと見られています。
観光施設や飲食店も通常営業を再開し、「観光客お断り」の張り紙を目にすることはほとんどなくなりました。感染対策を前提とした受け入れ体制が整い、島民の間でも観光への理解が広がっています。
リモートワークの浸透で移住者が増加
コロナ禍を機にリモートワークが普及し、都市部の仕事を続けながら石垣島で暮らす人が増えています。
これにより、観光目的の一過性の訪問とは異なる「定住型」のライフスタイルが広がっています。
移住者の中には、島内で新たなビジネスを立ち上げるケースも多く、地域経済に新たな活力をもたらしています。
石垣島経済の回復と多様化
観光業の復活に伴い、石垣島の経済状況も徐々に回復しています。
一時的に失業していた人々の職場復帰も進み、新たな観光サービスや特産品の開発が活発化。コロナ前よりも、産業構造の多様化が進んでいます。
持続可能な観光へのシフト
少人数・体験型ツアーが主流に
「量より質」を重視する観光スタイルが広がり、大型バスによる団体旅行から、少人数制のプライベートツアーや体験型観光へとニーズが移行しています。
これにより、観光客一人ひとりの満足度が向上するだけでなく、環境への負荷も軽減。持続可能な観光の実現に向けた前向きな動きとなっています。
環境配慮型プログラムの充実
石垣島では自然環境への配慮を重視した観光プログラムが増加中です。
例えば、
- ビーチクリーン活動:観光客も参加可能な清掃イベント
- サンゴ礁保護ツアー:海の環境を学びながら楽しめる体験型ツアー
- エコツーリズムの推進:自然に優しい観光スタイルの普及
これらにより観光客の環境意識も高まり、地域の自然保護に積極的に関わる人が増えています。
地域住民との共生を目指す観光へ
地域の文化や住民の暮らしに配慮した観光のあり方が、今、強く求められています。
観光事業者には、静かな生活エリアに対する十分な配慮が不可欠です。また、観光客にも島のルールや文化を理解し、敬意をもって行動することが望まれます。
こうした取り組みを積み重ねることで、観光客と地域住民との間に信頼関係が生まれ、誰にとっても心地よい観光地へと成長していくことが期待されています。
石垣島が直面する課題と今後の対策

ゴミ問題への継続的取り組み
観光客の増加に伴い、海岸部を中心にゴミ問題が深刻化しています。
対応策としては
- ビーチクリーンの定期開催
- 「ゴミは持ち帰ろう」キャンペーンの実施
- 観光客も使いやすいリサイクル施設の整備
啓発と実行の両面から持続可能な観光環境の維持が求められています。
交通渋滞の緩和策
観光シーズンの慢性的な渋滞に対しては、次のような取り組みが進んでいます。
- 公共交通の利用促進(観光路線バスの拡充など)
- 効率的な観光ルートを案内する観光タクシーの普及
- カーシェアやライドシェアなどの導入検討
文化財・神聖な場所への配慮強化
石垣島には御嶽(うたき)と呼ばれる神聖な場所が点在し、無断立ち入りによるトラブルも問題となっています。
主な対策としては、
- 案内看板の多言語対応(英・中・韓など)
- ガイドツアーでの文化的背景の説明強化
- 観光マップで立ち入り禁止区域を明示
こうした工夫により、観光と文化保護の両立が図られています。
【観光客向けガイド】責任ある石垣島観光のススメ

訪問前に知っておきたいマナーと心得
1. 島の文化と歴史を理解しよう
石垣島を訪れる前に、その文化や歴史について基本的な理解を深めておくことが大切です。
この島は、琉球王国時代から独自の文化を育んできた歴史ある場所。現在も方言、年中行事、伝統料理などが大切に守られています。
旅行前に島の背景を調べておくことで、現地での体験がより豊かになり、地元の人々との交流もスムーズに。ガイドブックや公式観光サイトを活用して、事前の情報収集をおすすめします。
2. 神聖な場所「御嶽」には立ち入らない
石垣島には40カ所以上の「御嶽(うたき)」と呼ばれる神聖な場所があります。
これらは地域住民の信仰の対象であり、無断での立ち入りは禁止されています。
一部の御嶽には案内板がありますが、目立たない場所も多いため、観光の際はガイドの同行や観光案内所での確認をおすすめします。
島の人々の信仰と文化に敬意を払いましょう。
3. 水資源を大切に
石垣島の水道水は、島内の地下水や河川水、海水淡水化によって供給されています。
離島という地理的条件から水資源には限りがあり、住民と多くの観光客で共有しているため、皆さんにも節水へのご協力をお願いしています。
- シャワーは短時間で
- ホテルでのタオル交換や洗濯は最小限に
- 蛇口の締め忘れに注意
島の持続可能性に貢献するためにも、小さな心がけを忘れずに。
4. 滞在中のマナーとエチケット
ゴミは必ず持ち帰りましょう
美しい自然を守るため、石垣島ではゴミの持ち帰りが基本マナーです。
- ビーチでは:ペットボトルやお菓子の袋は必ず持ち帰る
- 山道では:トレッキング中のゴミは袋に入れて管理
- 街中では:購入品の包装も適切に処分
「来た時よりも美しく」を合言葉に、自分のゴミだけでなく、見つけたゴミも一緒に持ち帰るとさらに◎。
騒音への配慮を忘れずに
住宅地と観光エリアが近い石垣島では、観光客の声や行動が住民の生活に直接影響します。
- 夜間(22時以降)は静かに
- 早朝(6時前)の外出は控えめに
- 複数人での移動は道を広がらず、譲り合いの精神で
島の静かな時間を大切にして、地元の人々との共生を意識しましょう。
5. 海で安全に楽しむために
石垣島の海はとても美しいですが、危険も伴います。安全対策をしっかりと行いましょう。
- 管理されたビーチを利用する:ライフガードのいるビーチを選ぶ
- 潮の流れや天候を確認する:遊泳前に現地の最新情報をチェックする
- 危険生物に注意する:ハブクラゲ、ガンガゼ(ウニ)、オニダルマオコゼなどに触れないよう注意
- サンゴを保護する:サンゴの上に立ったり触れたりせず、マリンシューズを着用して海底を傷つけないようにする
美しい石垣島の自然を大切にしながら、安全第一で海の時間をお楽しみください。
【2026年最新情報】石垣島観光の今とこれから

現在の受け入れ体制
感染対策の現状
2026年現在、石垣島では引き続き基本的な感染症対策が行われています。
ホテルや飲食店、観光施設では、定期的な換気・消毒が実施され、訪れる旅行者が安心して滞在できる体制が整っています。
ただし、感染症の流行状況によっては対策レベルが変更される可能性もあります。旅行前には、石垣市公式サイトや観光協会などから最新情報の確認をおすすめします。
観光施設の営業状況
現在、石垣島の主な観光スポットはすべて通常営業中です。
- 川平湾:グラスボート・SUP・カヤック体験が通年実施中
- マリンアクティビティ:シュノーケリング、体験ダイビングツアーが活発に開催
- 離島ツアー:竹富島・西表島・波照間島などへの定期船が通常運航
- ナイトツアー:星空観察、ナイトサファリなどの夜間体験も復活中
アクティビティを満喫したい方は、現地ツアーの予約サイトや旅行会社で事前にプランを確認しておくと安心です。
混雑緩和のための予約制導入スポット
人気観光地では、一部アクティビティに事前予約制が導入されています。
- 川平湾のSUP・カヤック体験:繁忙期は予約必須
- 青の洞窟ツアー:参加人数制限あり、安全管理のため事前予約が望ましい
- 星空フォトツアー:少人数制のため、早めの予約がおすすめ
混雑を避けて快適に楽しむためにも、早めの計画と予約を心がけましょう。
今後の展望と観光施策の方向性
持続可能な観光の実現へ
石垣島では「自然と共生する観光地」を目指し、持続可能な観光モデルの構築が進められています。
- 観光客数の適正管理:島のキャパシティに見合った来島数の維持
- 環境保全との両立:自然への負荷を抑えたアクティビティの推進
- 住民との共生:地域社会との調和を図る観光開発
文化資源の保護と活用:御嶽や伝統芸能など、島のアイデンティティを尊重した活用
「観光の質」を重視した取り組みにより、リピーター層の獲得と地域満足度の両立が目指されています。
インフラ整備の取り組み
観光の受け入れ基盤を支えるインフラ整備についても取り組みが進められています。
水道インフラの強化
石垣市では防衛予算を活用した原水調整池整備計画(事業費50億円規模)が2027~30年度に予定されており、安定供給体制の強化が図られています
観光案内の多言語化
石垣市観光交流協会をはじめとする観光関連施設において、案内情報の多言語対応が進んでいます
文化体験と地域活動の取り組み
石垣島では、地元の伝統文化を活かした観光体験や地域活性化の取り組みが行われています。
伝統文化体験の提供
石垣島三線体験教室では観光客が気軽に三線に触れることができ、石垣焼やシーサー作りなど手ぶらで楽しめる陶芸体験も提供されています
伝統工芸の継承
八重山みんさー織などの伝統的工芸品の技術継承が行われており、文化の保存と観光が両立しています
地域文化の発信
石垣市民会館での「郷土芸能の夕べ」や「石垣島やきもの祭り」など、八重山の伝統文化を紹介するイベントが定期的に開催されています
地域活性化イベント
石垣マルシェのような地域活性化と自然保護の両立を目指すプロジェクトも実施されています
これらの取り組みにより、観光客が石垣島の文化に触れながら、地域の文化継承や活性化にも貢献する仕組みが形成されています。
石垣島が歓迎する“これからの観光客像”
石垣島が理想とするのは、観光を「自分事」としてとらえる来島者です。以下のような意識を持つ観光客が、島と長く良好な関係を築く鍵になります。
- 自然と文化を尊重する人:神聖な御嶽や伝統行事への理解がある
- 地域に貢献しようとする人:地元経営のお店やガイドを積極的に利用
- 責任ある行動ができる人:ゴミの持ち帰りや静かな滞在を心がける
- 何度も訪れたくなる人:単なる観光地ではなく、心の拠り所として島と関わる
石垣島は、観光客と地域住民が共に幸せになれる“Win-Win”の関係構築を目指しています。
まとめ:「石垣島に観光客は来ないで」の言葉の真意
「石垣島に観光客は来ないで」という言葉は、コロナ禍という特殊な状況下で、島民の生命と健康を守るために発せられた切実な声でした。
当時の石垣島は、限られた医療体制と「沖縄の離島は安全」という誤解の拡散により、深刻な危機に直面していました。
現在の石垣島は、観光客を温かく迎え入れています。コロナ禍を経験した島民と観光業界は、「持続可能な観光」という新たな価値観のもと、環境と地域社会に配慮した観光のあり方を模索し、実践しています。
石垣島の美しい自然と豊かな文化は、多くの人々にとって貴重な宝物です。この宝物を未来の世代に継承していくためには、観光客一人ひとりが責任ある行動を取ることが重要です。
これから石垣島を訪れる皆さんには、島の歴史と文化を理解し、環境に配慮し、地域住民との共生を心がけていただければと思います。
そうすることで、あなたの石垣島旅行は単なる観光以上の価値ある体験となり、島の持続可能な発展にも貢献できるでしょう。
石垣島では、自然環境の保護と観光の両立を目指した様々な取り組みが行われています。ぜひ、この美しい島で責任ある観光を実践し、素晴らしい思い出を作ってください。

